|
「かーいとっ!お待たせ〜。」 待ち合わせに現れた青子は、赤いブーツにフェイクファーのついたウエッジウッドブルーのGジャン、 そして・・・ 「なっ、オメエなんでそんな短いスカート穿いてんだよ!」 「え?だって、恵子がデートは勝負だからこれがいいって。」 おかしかったかなぁ、などと、見当違いな事をいいながら、青子は目の前でくるくるまわる。 「・・・おまえさ、勝負の意味わかってる?」 「かわいいかっこして、彼氏を喜ばせる?」 いやまあ、当たらずとも遠からずなんだけど。 その先に待ってるのが何か、こいつはわかっちゃいねぇと思う。絶対。 「・・・とりあえず、行くか?」 「うんっ!」 元気よく返事をして、青子は快斗の手をとる。 「おわっ、お前なんで手・・・。」 「だから!今日の青子は快斗の彼女でしょ?ささ、レッツゴー♪」 「ヘイヘイ、もーこうなりゃとことんまで付き合ってやるぜ!」 そういって、快斗はつながれた手を振りほどき、その手を自分の腕にからませた。 一瞬、青子は驚いて動きが止まったが、ぎゅうっと快斗の腕にしがみつき 「そうこなくっちゃ!」 嬉しそうに笑った。 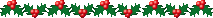 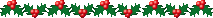 どうしてこんなことになっているかといえば。 それは冬休み直前の休日。 例年なら、パーティの準備だ買出しだと大忙しのこの日、 快斗は青子の家で、まったりとお茶を飲んでいた。 「なぁ、今年はなんでパーティやんねーの?」 ちょっとの期待を込めて聞いてみる。 「だって!みんなデートだとか旅行だとか言って人が集まらないんだよね〜。 まったく誰よっ!クリスマスは恋人達の日なんて決めたのは!!」 青子はぷんぷんという表現がぴったりくるようなかんじで怒りながら 快斗の持ってきたミルクレープにぶすぶすフォークを突き刺している。 「俺が知るわけねーだろ。」 聞いた俺がバカだった・・・。 大体、高校生になってみんなでパーティなんて、いまどきやんねーぜ? と言ってやりたかったが言葉は飲み込んでおいた。 これ以上怒らせると、後々ほんっとーに面倒になるのは、今までの付き合いで身にしみて わかっているつもりだ。 「あーあー、今年のクリスマス、つまんないなー。」 そういって、ごろりと寝転がった青子の目線が 勉強机の上のピンクの表紙の文庫本でとまる。 「・・・青子も胸がきゅんきゅんするようなデートしたいな・・・。」 ぽつりとつぶやいた独り言。 それは普通の人なら聞き逃しているような小さな声だったけれど この俺が聞き逃すわけなんてなくて。 コノヤロー、だったら目の前にいる男をもうちょっと意識しろよと 猛烈な脱力感に襲われた時、快斗にとってのビックリ箱は がばっと起き上がり、またも予想外のことを言い出した。 「そうだ!快斗!!24日は青子とデートしよう!」 「へ?」 嬉しい、という感情よりも先に疑問符が頭の中をかけめぐる。 一体青子の頭の中では、なにがどうなってそういう結論になったのか。 コイツの場合、絶対なにか人とは違った経路でこの結論に行き着いたはずだ。 期待しては肩透かし・・・ いままでの苦い経験から、疑い深くなっているのは仕方のないことで。 そんな快斗の葛藤には気づかず、青子はどんどん続ける。 「この前のトロピカルランドみたいなのじゃなくって、その日はね、2人は恋人なの!!」 「はぁぁぁ〜?」 ま、また突拍子もないことを・・・。 ってゆうか、24日限定ってなんなんだよ。 どうしてそこで、「ずっと」という発想につながらないのか・・・ 考え込んでいた俺を見て、青子が不安そうに尋ねてきた。 「ねぇ。ひょっとして快斗も24日予定はいってるの?」 「・・・別にねーよ。」 とりあえず その上目遣いはよしてくれ・・・。 平静を装って答えたつもりが、ぶっきらぼうになってしまった。 でも、ここで下手にからかったり、意地でも張って じゃあ白馬君と♪なんていわれたらえらいことだ。 「じゃあ、決まりね!ふたりでさみしいクリスマスを楽しくしよう!! あ、プレゼントだってちゃんと彼女にあげると思って選ぶんだよ!」 「ヘイヘイ・・・。」 イエイ!そんなかんじで青子は嬉しそうに親指を出した。 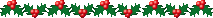 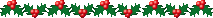 待ち合わせの後、ふたりが向かった先は、海浜公園とそこに併設されているショッピングモール。 普段は家族連れでにぎわうここも、クリスマスのイベントが多数催され、 今日はクリスマスイブのカウントダウン花火大会が開かれるということもあって どちらかといえば男女ふたり組の方が多いようだった。 駅からショッピングモールまでの並木道は、キレイに装飾され 夜ともなれば、きっとぴかぴかのツリーに変身するに違いない。 人ごみの中を、今は手をつないで歩く。 昔は、どこに行くにもこうしていたのに。 何時からだろう、どちらからともなく つながなくなってしまっていた。 「なんか、なつかしーね。昔はいっつもこうやって出かけてたのに。」 青子も同じことを考えていたのか、そんなことを言い出した。 「俺は、いつだってオッケーだぜ?なんなら毎朝手ぇつないで登校すっか。」 「・・・いいよー。できるもんなら、ねっ!」 そういって、つないだ手をぐるんと大きくまわす。 「言ったな、覚えてろよ!」 話している内容は、いつもと同じ、とりとめのないものだったけれど いつもと違うのは、つないだ手から伝わってくるぬくもり。 いつの間にか、俺の手は青子の手をすっぽりつつめるほど大きくなっていて。 青子の手は、むかしと変わらずふにゅふにゅと柔らかく、そして暖かかった。 ショッピングモールの入り口には、ぴかぴかのツリーが飾られ、 その下では、サンタクロースが数人、子供たちにお菓子の入った靴下を配っていた。 きょろきょろとめずらしそうに、ツリーを眺める青子に、 サンタのひとりが笑いながら靴下を渡してくれた。 青子は、わぁ、ありがとう。なんていって嬉しそうに受け取ったものの ん?って表情になって。 「ちょっと、これって青子がお子様って事ー!?」 ぷんぷん怒ってる姿は、まさにお子様のソレだったけれど。 「青子が特別かわいかったからじゃねーの?」 「なっ・・・。」 普段の快斗の言動から「そーそー、青子はお子ちゃまだもんな〜♪」なんて からかわれるに違いないと思っていたのだろう。 思いもかけないことを言われ、青子は顔を真っ赤にしてそっぽ向いてしまった。 「青子ちゃん、顔赤いぜ?」 「そ、そんなことないもん・・・あ、青子のど渇いちゃったな!」 照れ隠しのごまかしに、そんなことを言い出して。 「はいはい、お姫さま。なにがお望みですか?」 「・・・冷たいりんごジュース。」 「承知いたしました♪買ってきてやるから、ここで待ってろ。」 あん時の青子の顔・・・。笑いを抑えるのに必死だった俺は 青子に背を向けた瞬間、こらえきれずにふきだしてしまった。 青子にバレてなきゃいいけど。 お姫様ご所望の品は、目の前の売店には置いてなくて。 少し離れたジューススタンドへ行って戻るまで、 それでも5分とかかっていないはずなのに 戻ってみると、青子はなにやら軽そうな感じの男に声をかけられていた。 油断もスキもねぇ・・・。 とりあえず、早急に害虫を駆除すべく、ずんずん近づいていくと 2人の間では、思いもかけない会話が交わされていた。 「ごめんなさい。今日は彼氏とデートなの。」 いつもだと、なんだかんだで話を聞いている青子が、きっぱりと断ってる。 しかも、「彼氏」とデートだって。硬くなってた頬がすこしゆるむ。 「でも、君を置いてどっかいっちゃってるじゃん?」 しかし、コレだけはっきり断っているというのに 男は、すぐにはあきらめず、さらにナンパを続行する。 そんな男に、青子はさらにかぶせるように言い放った。 「それは、青子のためにジュース買いに行ってくれてるだけだし。 とにかく、青子たち、らぶらぶなんだから!ごめんね!!」 イブ当日の今日。全く見込みのない相手にあまり時間はとれないのか、 満面の笑みと、初対面の相手に臆面もなく「らぶらぶ」などという 彼女に毒気を抜かれたのか。 男はさきほどの粘りはドコへやら、驚くほどあっさりと引き下がり、 次の獲物を探しに行ってしまった。 彼氏とデート らぶらぶ・・・ およそ、普段の青子からは絶対飛び出さないであろう それらの単語が頭の中でリフレインする。 今日限定とはいえ、青子の口から飛び出したそれらの単語はひどく魅力的で。 しかも、その対象は他でもない自分である。 「ねぇ快斗、顔赤いよ?走ってきてくれたの??」 青子に声をかけるまで、俺はその場にぼうっと突っ立っていた。 「ああ、まあな。ホレ、お望みのりんごジュースだぜ。」 「ありがとう。」 らぶらぶー そんなかんじの笑顔で、青子はうれしそうにりんごジュースを受け取った。 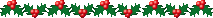 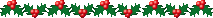 くるくるまわるテーブルで飲茶が食べたい。 そんな青子のリクエストに答えて、飲茶も食べれる中華料理店に入る。 夕飯時を少し過ぎていたものの、休日の店内にはまだ多くの食事客がいて やはり2人連れでは広い円卓の席へ座ることは出来ず、窓際の2人がけの席に通された。 窓からは、さっきの並木道のイルミネーションがよく見えて。 窓側の席はカップルばかりのところを見ると、店側のサービスなのかもしれない。 「くるくるできなくて、ちょっと残念だな。」 窓の外を眺めながら、ぷうっとほっぺたを膨らましてる姿は、やっぱり子供みたいだったけれど、 窓の外の淡い光に照らされた横顔は、いつもの青子じゃないみたいだった。 「まぁ、いいじゃねーか。またくれば。」 「そうだよね。お店は逃げないし、またいっしょに来ればいいよね!」 「そーそー。ホレ、なに食うか決めろよ。」 そういってメニューを広げる。 「じゃぁね、コレ!お魚と白身のスープっておいしそう。」 「おまえ・・・ソレは俺に対する挑戦か?」 「えー、じゃあこっちは??」 「魚香肉絲・・・って、めっちゃ魚って書いてあるだろーが!!」 「だいじょうぶ、これ肉料理だからー。」 そういって、ちゃっちゃと注文を決めて、さっさと頼んでしまった。 オイオイ、カンベンしてくれよ・・・。 一体なにが食卓に並ぶのかと気が気でない俺をよそに 青子は、なにやら がさがさと鞄のなかをひっかきまわしている。 ようやく探し物が見つかったのか、顔を上げた青子は、満面の笑みで。 「快斗、メリークリスマス!!」 そういって少し小さな包みを差し出した。 「これ、プレゼントか?」 「うんっ、あんまり時間がなかったんで小物になっちゃったんだけど・・・。」 中からでてきたのは、てぶくろ。 黒とダークブルーので編まれた模様が ところどころ微妙なのは手作りの証で。 でも、それがかえって暖かそうな印象を与えていた。 「快斗、冬になると手が冷たくなってたじゃない?さっき手をつないだ時もひやっとしたよね。 マジシャンは手を大切にしないと、っておじさま言ってたから。」 「・・・ありがとう、青子。」 お礼をいった俺に、青子 不器用だからごめんね?なんていいながら、 ちょっと恥かしそうに笑いかける青子。 そんな彼女が、短期間の間にがんばって作ってくれたのかと思うと その気持ちのほうがうんとうれしかった。 「なぁ、俺のなんだけど、ちょっとここじゃマズイんだよな。」 「へ?どういうこと??」 「とりあえず、今はコレだけな。」 そう言って。 ぽん、と青子の目の前にさしだしたのは、1輪の真っ赤なバラ。 「えへへ、ありがとう。じゃあ、楽しみにしておくね。」 青子は、そっとバラをテーブルの上に置いた。 「失礼いたします。」 料理と一緒に運ばれてきたのは、少人数用の机にも載せれる小さなターンテーブル。 「わぁっ、こんなのあるんだ!」 なんだかんだ言っても、青子が選んだ料理の中に天敵はいなくて。 奴が食卓をくるくる泳ぎ回る姿を見ることはなかった。 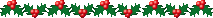 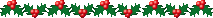 食後の腹ごなしにショッピングモールの中をぶらぶらと散策する。 花火まではまだ時間があった。 ふたりは、6階分をぶち抜いた吹き抜けのある多目的広場までやってきた。 「よし、ここならオッケーだな。」 「なにが?」 「青子へのクリスマスプレゼント。青子、さっきの花出してみ。」 ベンチに腰を下ろし、青子が握り締めていた花を差し出したその時、 わぁっ という歓声がすぐ近くで聞こえた。 なにが起こったのかと周囲を見回すと、ピエロがラッパを吹きながら二人が座っているベンチの方へと 歩いてきた。 どうやら広場で大道芸人のショーがはじまるようだった。 どんどん人が集まり始め、プレゼントを渡すという雰囲気ではなくなってしまったが ふたりも観客に混じって、次々と披露されるピエロの見事な技に目を奪われていた。 ジャグリングなどをひととおり披露した後、ピエロはマジックをはじめた。 たまたま、いちばん前にいた快斗が呼ばれ、ピエロを手伝うような形になった。 渡されたシルクハットを確認するように指示され、 快斗の手にしたシルクハットから、ピエロの掛け声とともに花があふれ出る。 わぁっと巻き起こった歓声につられて、快斗に、ちょっとしたイタズラ心が起きた。 シルクハットの花を、女性客に配っているピエロの後ろで 快斗はカウントダウンを始める。 「ワン・トゥー・スリー!!」 花でいっぱいだったシルクハットの中から白い鳩が飛び立って。 その勢いで、観客達の上に花吹雪が舞い散る。 観客もピエロも。 突然のことに一瞬言葉を失っていたようだったが、 すぐにどっと大きな歓声と拍手がまきおこった。 快斗の周りに人が集まり、先ほどのピエロもニコニコしながら握手を求めてきた。 そんな快斗の所に女の子の2人組が近づいてきた。 「お兄さん、スゴイね!」 「ねぇねぇ、ひとり?よかったら、今から私たちと花火見にいかない?」 それは明らかに逆ナンパで。 ひとりって?って、青子の奴は・・・と周りを見回すと、 なんとなく遠慮がちに元のベンチに腰掛けて 喝采を浴びている快斗をながめていた。 ちょっと寂しそうに見えるのは、絶対気のせいじゃないはず。 「悪ィ、俺、デート中なんだ。」 そういい残して、俺は青子の待つベンチへと戻った。 「快斗、よかったの?」 青子のところへ戻って、第一声はそれで。 「へ?なんで。」 「だって、あの子たち・・・。」 コイツは、どうしてこういうときにヘンに気を使うのだろうか。 「なぁ。」 思わず、不機嫌な声になる。 「な、なに。」 「いま、俺の彼女は青子なんじゃねーの?」 「あ・・・う、うんっ。そう、そうなんだけど。」 「それに、オメーだってさっき・・・。」 「へ?」 「いや、なんでもねー。」 そのまま、すとん、と青子の横に腰掛けて、さっきの仕切りなおしとばかりに 今度は青子にだけ聞こえるちいさなカウントダウンをはじめる。 ワン、トゥー、スリー!の掛け声とともに青子の手の中に現れた小さな箱。 「わぁ!」 「あけてみ。」 中から出てきたのは、ガラスビーズの指輪。 水色と透明のガラスを組み合わせて作られたそれは 青子をイメージして快斗が作ったものだった。 「悪ぃな、ほんとはもっとぱーっと出すつもりだったんだけど さっきのピエロんとこでネタ使っちまったから・・・。」 「ううん、とってもうれしいよ、快斗。それに・・・」 青子は何か言おうとしたが、そこで黙ってしまった。 俺は、迷わず青子の左手を取って、薬指に指輪をはめた。 「あ、そこ・・・、いいの?」 「だから!お前、彼女なんだろ?」 「あ、うん。そう、そうだよね。」 青子は、曖昧な感じで返事して。 指にはめられたそれをじっと見つめていたが、 俺のほうを見て、今度こそ本当に嬉しそうに笑った。 「よし、そろそろ花火の場所とりにでも行くか?」 「うんっ!」 手をつないで。 ふたりは暖かいショッピングモールから外へと向かった。 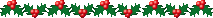 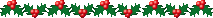 「さむいー。」 結局、ふたりが腰を落ち着けたのは、 海岸からはちょっと離れたところにある公園。 海沿いのプロムナードやショッピングモールの屋上は 花火を見るための人でごった返していたが さすがにここまで戻って来る人はあまりいないようだった。 子供たちが草ぞりをするための小高い丘があるので 少し遠くはなるが、花火は見えないこともなさそうだった。 「ここなら魚いねーしな♪」 「えー、夜だから魚いたって見えないよ〜。」 「わかんねーぜ?」 そんなバカ話をしながら、草ぞりの丘に登る。 頂からは、遠く海を挟んで光の洪水が見える。 「キレーだねー。」 そんなことを言いながら夜景を眺める青子。 海から離れているとはいえ、吹いてくる風はやっぱり湿り気を帯びていて、どんどん体から熱を 奪ってゆく。 特に、今日の青子は短いスカートなんかはいているので、俺よりずっと寒いはずだ。 「青子、そんなとこつっ立ってねーでこっちこいよ。」 「うんっ。」 快斗はドコから持ってきたのか新聞を広げてその上に座っていた。 青子も隣に並んで座り、さっき防寒用にと購入したブランケットを広げる。 「快斗もいっしょに足入れよう、あったかいよ。」 そういって、ブランケットの端をちょっと持ち上げながら、 俺のほうにずりずりと近寄ってきた。 このままでもいいけれど・・・。 「バーカ、だったら、こっちの方があったかいぜ。」 そういって、座ったまままま青子の背後へとまわりこみ、 自分のダウンジャケットの中に、青子をすっぽりおさめる。 「今年は暖冬だけど、Gジャンだと寒いだろ?」 びっくりしたのか、青子は一瞬体を硬くしたが、 「ほんと、この方があったかいね。」 そういって、ブランケットをちょっと引き上げて、快斗の足を入れてくれた。 いつも並んで歩いていた青子。 いま、腕の中にすっぽりと納まっている彼女は やっぱりどこもかしこも女の子に出来ていて。 このまま強く抱きしめたら、ばらばらになってしまいそうだった。 ふわふわと髪から漂う甘い匂いと、何か話すたびに感じる彼女の息遣い。 こんなにも間近に青子を感じることができる。 こんな機会、この先めぐってくるのだろうか・・・。 そんなことを考えていたら、知らず腕に力がこもっていた。 話してる内容は、いつもどうりのとりとめのないことなんだけど。 快斗の声が耳元で、しかも後ろから聞こえるのが不思議で。 聞きなれた快斗の声なのに違う人の声みたい。 快斗の声って、こんなに低くてやさしかったっけ? さっきは背中に感じるあったかい重みと、廻された腕の太さにちょっと驚いてしまった。 ああ、快斗はほんとに男の子なんだ、って。 暖かくて、快斗の腕の中は居心地がよすぎて。 ずっとこうしていたいな・・・。 そんなこと考えていたら、まわされた腕がぎゅって強くなって。 ひょっとして、快斗もおんなじこと考えたのかな。 ・・・どうしよう。 今更だけど、今日が終われば二人の関係は今までどおり幼馴染。 そう思うと、胸がぎゅうっと押しつぶされそうに苦しくて。 会話が途切れて。 先に口を開いたのは青子だった。 「楽しかったね、今日は。」 「おう。」 カウントダウンの花火が始まる。 時計の針が日をまたぐまで、あと5分。 「花火、キレイ・・・。」 「そうだな。」 さっきまでと違う、声のトーン。 いま、青子はどんな顔してるんだろう。 「ねぇ、快斗。」 ぐるっと体を廻して、快斗を見上げる。 快斗はどうした?ってかんじでちょっと笑って ・・・やっぱり、こんな快斗なんて青子知らないよ。 もう、会えなくなっちゃう。もうひとりの快斗。 さっきまで、あんなに元気だったのに。 楽しかったね、って言ってたのに。 振り向いて、俺の名前を呼ぶ青子はとってもさみしそうで。 どうした?って笑いかけたら、青子は俺の胸のところに 額を当てて、ぽつりとつぶやいた。 「今日、ほんとに楽しかった。青子、ほんとに快斗の彼女になったみたいだった。」 「青子?」 「・・・もうすぐ、魔法解けちゃうね。」 そういって、ぎゅっと俺のダウンジャケットの端を握る。 それって・・・。 「・・・じゃあ、俺がも一回青子に魔法をかけてやる。」 「え?」 言葉の意味をわかりかねたのか、そろそろと顔を上げた青子。 そのまま抱き寄せて、もういちど腕の中に閉じ込める。 「俺が、ぜってー解けねーような、とびきりのやつ。かけなおしてやる。」 「かいと・・・。」 12時を告げるシンデレラの花火。 同時に、ふたつの影がひとつになった。 |